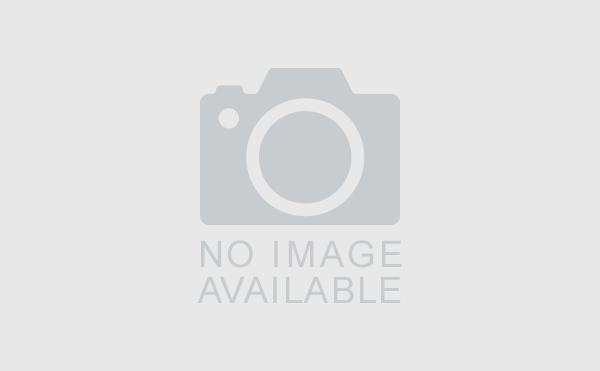11月11日(会報11月号「主張」)
11月11日は「いい日いい日」の語呂合わせから、厚生労働省が「介護の日」、と制定している。日々、老老介護を目の当たりにしながら診療を続ける、そんな令和7年の11月11日に財務省は、財政制度等審議会財政制度分科会に「日本の開業医の給与水準は日本の勤務医の給与やOECDの開業医(自営)と比較して大きく乖離している」と診療報酬適正化を求める主張をした。財務省の資料によると、日本の開業医は、他のOECD主要国の開業医の1・5倍の収入がある、とのことである(国内全産業の平均給与に対してOECD自営医師平均が2・9倍に対して日本は4・5倍)。しかし、日本以外のOECD主要国における開業医の役割は、GP: GeneralPractitioner(日本で目指すところの〝かかりつけ医〟)である。フリーアクセスではなく、専門性もない。一方で、日本における開業医は、すでに専門医を取得し、総合病院などで部長クラスを務めた医師であることが多く、フリーアクセスの仕組みと合わせて、総合病院への負荷を減らす重要な役割を担っている。神の目を持つ万能なGPが適切な判断をして、速やかに総合病院へアクセスできる仕組みが成立していれば、英国型のGP制度などは理想的であろう。しかし、残念ながら英国ですら、患者が急性疾患でGPを受診し、GPが紹介状を作成し、専門医に診てもらうのに日をまたぐ状況である。下手をすると数週間待ちなども生じている。〝急性疾患〟だというのに。日本では専門医を持つ開業医は、自ずと地域の総合病院とも強い繋がりがあり、電話一本で必要な専門的治療を受けられる環境に患者をつなぐことができる。全く他のOECD諸国の自営医とは違う役割を持っている。患者の正しい選定と素早い総合病院との連携。これは、現在負荷が強すぎる総合病院の勤務医負担を減らす重要な役割である。まあ、その勤務医負荷が強すぎる状況に危機感を持った医師が、地域医療を支えるために開業医に転じている面があるため、当然ではあるが……。
日本の治療可能死亡率は、OECD平均よりも40%低く、生活習慣病の発生率も全体的にOECD平均よりも低い。国民の予防医療への支出割合(GDP比)がOECD平均の半分であることを考えると、日本における開業医がいかに重症化予防と生活習慣管理に尽力しているかが浮き上がってくる。在宅当番医、休日夜間救急、学校医、なども地域の開業医が担い手である。そんな開業医を執拗に叩いてくる財務省は、一体何がしたいのか。開業医そして医療の現場の産み出す果実は米国並みを求め、一方で支出についてはトランプ大統領がOECD国際課税ルールからの離脱をエクスキューズに今回提出資料から開業医の年収を省く徹底ぶり(米国は国際課税ルールからは離脱しているが、OECDからは脱退していない)。開業医を叩きたいがゆえの資料作成としか思えない。まずは、素直に日本の医療制度の優れた部分を認識し、現在明らかとなっている地域を支える総合病院勤務医の負荷の軽減の仕組みを構築すること。そこに適正な支出をし、持続可能な国民の健康を守るシステムを維持することが重要である。医療インバウンド等のような企画に出費している場合ではない。
11月11 日は、財務省にとっては「いいな、いいな、開業医って羨ましいな」の日であったのかもしれないが、日々、現場で奮闘する医師にとっては、「一人ひとりに良(い)い医療を」の日である。いろいろ思うところはあるが、目の前に財務省職員が来たときには、変わらぬ丁寧な診療をするであろう全国の開業医に乾杯。