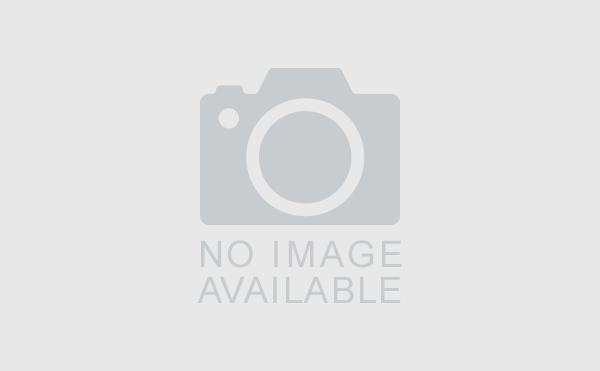1点=X円(会報8月号「主張」)
物価高がとまりません。例をあげます。業務用の米10㎏が令和5年10月に3200円でした。令和7年8月現在7000円です。業者からは、令和7年10月からの値上げ要請があります。ネット、スーパーを見ますと、妥当な値上げのようです。値上げをのまないといけない状況です。業務用の米が2年足らずで倍以上になるというのは、事業を続ける上で本当に大きな負担となります。特に医療機関では、診療報酬という形で収益が固定されているため、経費の高騰は経営を直接圧迫します。
物価高はどこまでいくのでしょうか。どこまであがっていくのでしょうか。
原因を考えますと、いくつか考えられます。1番目に国際情勢とエネルギー価格の影響です。ウクライナ情勢や中東地域の地政学的リスクが解消されれば、エネルギー価格は安定に向かい、物価高の緩和につながります。しかし、これらの問題が長期化すれば、物価高も続く可能性が高いです。第2番目にコロナ禍で生じたサプライチェーンの混乱も依然として影響しています。経済活動の再開に伴い需要が回復する一方で、部品や原材料の供給が追いつかず、品不足から価格が上昇する傾向が見られます。3番目に、世界的な人手不足や最低賃金の上昇による人件費の増加も、企業が製品価格にコストを転嫁せざるを得ない状況を生んでいます。特に日本は少子高齢化の影響で、働く人口が急激に減少しています。4番目としては、トランプ政権の関税政策が物価高を加速させる要因となり得ます。トランプ氏が提唱する「相互関税」や「一律関税」が導入されると、輸入品のコストが直接的に増加し、それが最終的な価格に転嫁されます。これは日本国内の物価にも影響を及ぼします。5番目に日本の金融政策です。日本銀行が金融緩和を続けるか、それとも金利を引き上げるかによって、円安の進行度合いが大きく変わります。金融緩和が続けば円安が加速し、輸入物価がさらに上昇する可能性があります。現在日本の住宅ローンの7割が変動金利だそうです。日銀の植田総裁も金利を上げにくいので、金融緩和が続くのではないでしょうか。これは植田総裁が悪いわけでなく、前総裁の黒田総裁から引き継いだ流れを止めにくい状況です。誰がやっても金融緩和を選択せざる状況になる可能性が高いのではないでしょうか。
以上の状況から、医療機関の経費が増大しています。一方、収入面から考えてみますと、医療機関の収入は大幅に減少しています。昨年2024年内科系のクリニックでは、大幅に診療報酬を減らされました。それにもかかわらず、2025年4月23日に開催された財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会での提案では、「診療報酬1点=8円」が話題になりました。中医協が〝点数配分の中身〟を議論するのに対して、財政制度分科会は〝財政的に増減できるか〟という枠組みや方向性を与える立場にあり、重要な意味を持ちます。この会議で、財務省は医師の地域偏在是正を目的として、診療報酬の地域別単価制度の導入を提案しました。具体的には、現行の全国一律「1点=10円」の診療報酬単価を、診療所が過剰な地域では「10―β円」に引き下げ、不足している地域では「10+α円」に引き上げるというものです。この提案では、具体的な数値として「8円」という金額は示されていませんでしたが、「1点=8円」という情報がリークされました。多くの医師や医療従事者からは、「1点=8円では経営が成り立たない」といった懸念の声が上がっています。財務省特有の極端な意見の観測気球をあげて、反応を確かめているものと思われます。実際はかなり緩和すると思われますが、ひどい話です。
支出は増大、収入は減少では、今後閉院するクリニックが増加します。 地方における医療は維持できなくなりますが、政府はきちんと現状を理解しているのでしょうか。