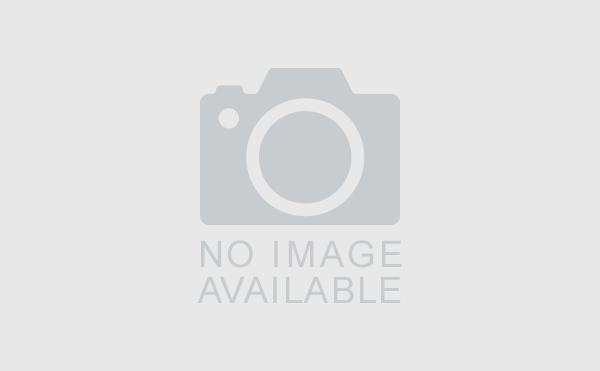高齢者をターゲットにした負担増施策の中止を(会報9月号「主張」)
1960年、岩手県沢内村から始まった老人医療費の無料化は、1969年に東京都で医療費助成制度が創設されるなど地方単独の福祉医療制度として全国に広がる中、1973年に国の制度となり、「福祉元年」と言われた。
ところが、1980年以降の医療費抑制策(臨調・行革路線、悪名高き1983年の「医療費亡国論」)により、高齢者医療は負担増の方向へと進み始め、2008年の後期高齢者医療制度の施行からはその流れが加速していく。そして現在も進行中の「全世代型社会保障の構築」に向けた議論が2020年から始まり、70歳以上の高額療養費負担上限の見直し、保険料軽減特例の見直し、といった制度改定が行われた。2022年10月に一定所得者(年収200万円以上)である75歳以上の医療費窓口負担が1割から2割に引き上げられたのもこの流れの1つである。
75歳以上の医療費窓口負担2割化をめぐる審議の際、協会・保団連では中止を求める国会請願署名に取り組み、70万筆を超える署名には多くの国民から「負担増は困る」との声が反映されていた。当時はコロナ禍であって、世界情勢の悪化や円安の影響による物価高騰が押し寄せてきており、国民生活への影響は甚大で、窓口負担2割化は高齢者の受診抑制を招き、健康悪化につながることが指摘されていた。厚労省は法改正時に「生活収支に余裕があるから窓口負担増の吸収は可能」「配慮措置を講じており必要な受診は妨げられない」などと説明していたが、2023年9月に審議会へ示した影響調査では、2割負担導入以降、2割負担の人の受診日数(月)は大きく落ち込み、1割負担の人の受診日数(月)よりも低位で推移し、「配慮措置」があっても受診控えが起きている事態
が明らかとなった。「配慮措置」とは、対象患者の外来受診における1か月の「『窓口負担増加額の上限』を3000円まで」とするものであるが、複雑な仕組みで分かりにくく、負担軽減の効果も薄いと指摘されていた上、開始後3年間の時限措置という梯子はずしとなっており、本年9月末終了の期限を迎えようとしている。
全世代型社会保障は、「世代間、世代内での負担の公平化を図る」「年齢ではなく『能力に応じた負担』を求める」ことを理念としており、そのもとで給付抑制、負担増が検討されている。とりわけ、「負担は現役世代、給付は高齢者となっている」と世代間の分断を図りながら高齢者に負担増を迫るものである。2023年12月に示された「全世代型社会保障・改革工程」では、高齢者の資産に着目した上で、金融所得や金融資産を勘案して保険料や入院時の室料、食費等を引き上げることや、3割負担となっている「現役並み所得者」の判定基準の見直しを求めている。さらに、2024年9月の「高齢社会対策大綱」では、現役世代の負担軽減を理由として、高齢者の窓口負担の引き上げ(3割負担の対象拡大)、高額療養費の自己負担限度額の見直しが盛り込まれた(高額療養費制度
の見直しは反対運動により凍結)。
止まるところを知らない高齢者をターゲットとした負担増施策は、政局が変動しても揺らぐ気配がない。責任ある財源論を示さずに、社会保障費削減ありきで、現役世代と高齢者の分断をあおり、医療費削減を声高に求める政党が台頭しているからである。高齢者はこれまでの日本の経済発展に貢献し、社会保障制度を支えるために保険料負担をはじめ財源確保に寄与してきた。物価高騰や年金の実質的な引き下げなど国民生活が悪化しているいまこそ、政府は、憲法に規定された国民の権利を守り、75歳以上の医療費窓口負担を2割から1割に戻すなど、国民医療の改善に向けた施策へと転換すべきである。