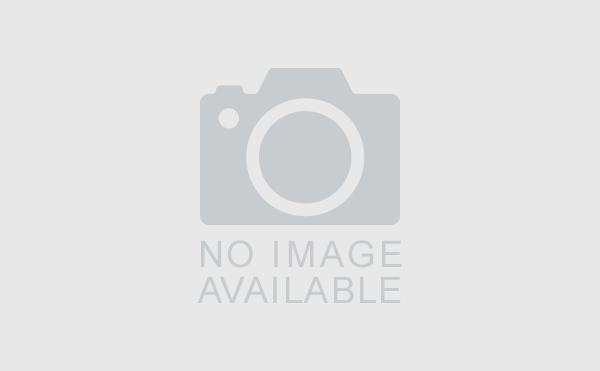適正な診療報酬を勝ち取ることが今こそ必要(会報10月号「主張」)
物価高騰が止まらない。1週ごとにそれを実感するほどいろいろなものが何度も値上げされており、嫌気を通り越してあきらめの境地にいる。しかし、物価高騰は日常生活の問題だけではないことが我々医療従事者を苦しめている。私たちが従事する医療現場においても物価高騰は止まるところを知らない。中でもどんどん高騰しているのが歯科で使う金属である。先週ついに30グラムが14万円超えとなった。現行の診療報酬では30グラムが約10万3000円。3万円以上の逆ザヤとなっているが、このマイナス分を負担するのは歯科医療機関となる。金属だけは3か月ごとに価格の随時改定があるが、12月改定でも30グラムが約11万4000円とのこと。価格急騰前の変動幅による算出計算であるため、「逆ザヤ」は広がるばかりである。つまり歯科診療では金属を使うたびに大きな赤字となる現状である。かと言って診療拒否もできない。医科の先生に「公示価格で決められているのであれば、各自が購入して準備するのではなく、政府からの配給にするべきではないのか」と言われたことがある。そのような発想は全くなかった。今は「逆ザヤ」であるが状況が反対になることもあったのだ。よく薬価差での利益分が話題となるが、歯科金属購入においても診療報酬との価格差で利益が出ることもあったらしい。そこから配給という考えが浮かばなかったのかもしれない。ともあれ、診療をすればするほど赤字となる現状を打破しなければならないだろう。
保団連が今年の2月から3月にかけて実施した「物価高騰に関する会員医療機関調査」の結果には驚きを隠せない。なんと歯科医療機関の9割以上は、光熱費・材料費、人件費などの高騰分が診療報酬改定ではまかなえていないと回答。現在の物価高騰の速度には2年に1度の改定ではついて行けず、振り切られるところも出ているのである。実際、2024年の歯科医療機関の倒産が過去最多であったことは、歯科医療界の経営困難を如実に表していると思われる。ところで、患者に渡す領収証には、ご丁寧に「厚生労働省が
定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています」と印字されている。物価高騰によって消費税負担も大きくなっている。仕入れ時に負担する消費税は診療報酬に含まれていると公言されており、材料費高騰分はもとより負担が増えた消費税分も歯科の経営に影響を及ぼしていることは間違いない。
また、歯科で問題なのは金属価格だけではない。外注技工物を作っている歯科技工士についての課題も多い。歯科技工士の減少や高齢化、歯科技工士の労働環境(長時間労働や低報酬など)である。これからどんどん高齢化が進む中、技工士不在となっては義歯が提供できなくなってしまうのではと懸念される。昔言われていた3Kではないが、確かに、長時間労働(休暇)、低報酬(給料)、感染の心配(危険)の3K労働とも言える。これら技工士問題のもとをたどると、歯科診療報酬が低すぎることにたどり着く。また、歯科技工所では物価高騰支援の補助金がもらえない県もある(山口県は厚労省が推奨しているにもかかわらず補助金の対象外とした)。歯科の抱える課題が多い中、「院長は儲けを分散する必要がある」と、昨年6月から技工料金をすべて10%アップした知人(神奈川県)がいる。技工士さんは喜ばれたそうだ。ただ、今の歯科経営状況の中、知人のように個人で対応できる歯科医師は少ないであろう。当会では全国の先陣を切って歯科技工士問題に取り組んでおり、それがいま全国の協会へと広がってきている。
適正な診療報酬を勝ち取れるよう真摯な議論や積極的な活動が今こそ必要な時である。