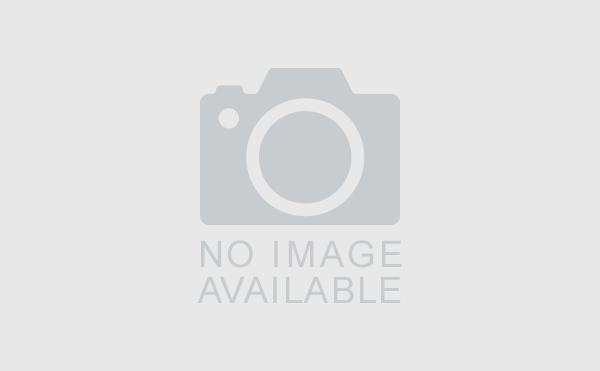物価高騰、手出しが増えてたまりません(会報7月号「主張」)
7月1日のある新聞、『値上げ食品5倍、2105品目』との見出し。
原材料費や人件費など幅広くコストが上がっている事が要因で、家計負担増が再び鮮明になっており、物価高対策が7月の参議院選挙の争点にもなっている。皆さんがこの原稿を一読されるときには、参議院選挙の結果も出ているだろう。
近年、電気代、ガス代、物価全般の上昇を誰もが肌で感じるようになった。医療機関経営の原資である診療報酬は、公的保険制度の中で厳格に定められているため、外来や入院での医療費が自由に変えられるわけではない。電気代やガソリン代、材料費の高騰、人材確保のための人件費増加等、コスト負担が年々重くのしかかってくるにもかかわらず、価格転嫁が難しい医療機関こそ、最もその打撃を受けている。諸経費増加分を診療報酬で吸収することは困難で、多くの医療機関が『持ち出し』、つまり自前で赤字を捕填せざるを得ない状況に迫い込まれているのである。経営者自身が報酬を削って運営を続けているケースもあるはずで、限界に達した医療機関が廃業すれば、地域医療にとっては致命的な損失になり得る。
帝国データバンクの集計では、2025年度上半期の医療機関の倒産件数は35件となっている。内訳は病院9件、診療所12件、歯科医院14件で、病院、歯科医院が過去最多、トータルでも過去最多を記録した。このままでは年間を通しても過去最多となるだろう。同社では、「診療報酬の推移が、医療機器、給食費、光熱費、さらには人件費の上昇分を賄うにはほど遠いレベルである」と指摘しており、10年以上にわたって診療報酬を引き下げてきた結果が今の状況を引き起こしていると言える。
政府や自治体は、付け焼刃的に「それを補うための支援金や補助金制度を創設した」と言うが、根本的な構造には手が届いていない。そして補助金申請要件には「対前年」という言葉が必ず付してある。要は、「自助努力した部分は補助金に該当しません。」という事だ。何とも言えない苛立ちを覚える。このような一時的な支援ではなく、物価や人件費の変動に柔軟に対応できるよう、診療報酬体系そのものの見直しが今求められている。
私たちが病気になった時、当たり前のように医療を受けられる環境を維持するには、医療機関の経営が健全であることが前提だ。政府は、「質が高く効率的な医療提供体制の確保」を名目に病床を削減する方針で、赤字経営に苦しむ病院に対して1床削減するごとに400万円の「人参」をぶら下げた。これで経営の健全化が図れるとは到底思えないが、それと引き換えに地域に必要な病床が消えてしまいかねない。コロナ禍で入院できずに亡くなってしまう事態を招いたことは記憶に新しい。空床であっても確保すべき病床はあるし、そのための施策も必要である。
目に見えにくい『赤字の連鎖』は、私たちの生活はもとより、国民医療そのものに跳ね返ってくる。医療はコストではなく、社会の基盤であるという視点を今こそ持つべき時期ではないだろうか。