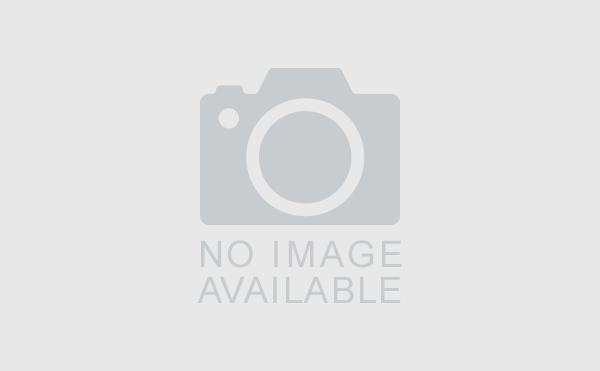政局の混乱にほくそ笑むのは官僚か(会報3月号「主張」)
高額療養費制度の見直しが凍結となった。この間の患者団体、協会・保団連による国民世論を巻き込んだ運動の成果であり、久しぶりの朗報であった。少数与党では、これまで当たり前のように無理を押し通してきた政権運営ができなくなり、野党の主張を否が応でも取り入れざるを得なくなっていることは、2025年度予算決定までの混乱ぶりが物語る。「教育無償化」や「103万円の壁」など与野党双方の駆け引きが行われている通常国会ではあるが、医療費削減政策だけは変化がないようである。
自民、公明、維新の3党合意により、社会保障費削減のための協議体設置が急がれており、検討にあたっては「OTC類似薬の保険給付の見直し」「応能負担の徹底」「医療DXの推進」「医療介護の成長産業化」といった具体策が並ぶ。維新にいたっては、「国民医療費の総額を年間で最低4兆円削減」と合意文書で謳う。46兆円(令和4年度)の医療費を10%近く削減する案など非現実的であり、荒唐無稽も甚だしいと言わざるを得ないが、振り返れば今回の政局の動きは、2012年の自民、公明、民主(旧)の3党合意による「社会保障・税一体改革」創設の動きを彷彿とさせる。アベノミクス社会保障改革もあって、官邸主導により推し進められてきた制度改革の基となるものだが、経済財政諮問会議、規制改革会議など大企業や経済界からの息がかかった政策は、脈々と受け継がれ実行に移されてきている。今回の自公維による3党合意は、これまで医療界などの反発によりできなかった改革を一気に進めますと宣言しているようなもので、結局、政局の混乱にほくそ笑むのは、改革を主導し、財源を握る官僚ということになる。
政策が提示される際、官僚は「分断」をあおることを忘れない。「世代間での負担の公平化を図る」=高齢者の窓口負担や保険料を見直す、あるいは、「能力に応じた負担を求める」=高額療養費制度の自己負担限度額を引き上げる、といった具合である。国民の団結を阻止する実に巧妙な手法である。さらに、「制度の持続性」をキーワードとして社会保障費の予算にのみ着目させる。例えば、児童手当の拡充など年3・6兆円規模の対策のうち、1・1兆円は社会保障の歳出削減で賄うとして、患者・国民の負担増を強いる一方で国費の支出は薄くするという策略である。国民に不人気のマイナンバーカード普及に2兆円以上もの税金を投入、アベノミクスにより儲けた大企業の内部留保金はこの10年間で200兆円以上も増加、年平均1兆円規模で増額する防衛費など、財源はあるところにはある。単純にそれを社会保障費に回せばよいのだが、国家の財布の使途を握るのは財務省たる官僚なのである。したがって、新たな協議体の議論には格段の注意が必要である。真っ当な財源論がなければ、診療報酬を引き下げて財源を確保するなどと誤った論点にすり替えられてしまいかねない。
翻って我々開業医の経営は危機的状況である。診療報酬の実質マイナス改定でベースアップもままならず、物価・光熱費高騰、医療DXによる不必要なコスト増など、負担に耐えられず閉院も相次いでいる。地域医療に貢献しようと開業した我々の夢や志は、政府によって打ち砕かれている。誤った施策に翻弄され、なぜこれほどまで痛めつけられなければならないのか。日医や日歯のように与党に迎合していては何も変わらない。「おかしなことはおかしい」と言わなければならない。いまこそ患者、国民を巻き込んだ保険医運動が輝くときである。高額療養費制度の見直し凍結の運動がそれを教えてくれている。今夏の参議院選挙に向けて、「健康保険証を残せ」の運動も盛り上げていきたいものである。(会報3月号「主張」)