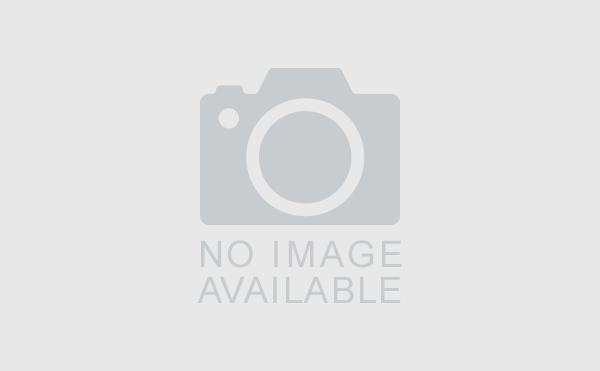強引な政策推進で疲弊した 医療現場を立て直す新たな1年に(会報1月号「年頭所感」)
昨年の1月1日は能登半島の大地震で、度重なる自然災害に日本中が不安と強い悲しみを覚えました。また医療界において2024年は厳しい一年となり、強い危機感を感じました。医療DXの名の下に様々なシステムがデジタル化するよう方向づけられ、満足に機能しないシステムに無理矢理組み込まれるように誘導されました。今年はその弊害が徐々に現れてくることになるでしょう。非常に奇妙に感じるのは、将来の展望を示さず遮二無二不明瞭で不安定なシステムを是とし、押し付けようとしていることです。まだインフラが整備されていないにも拘らず、莫大な税金を投入して医療DXを進める様は狂気としか思えません。新しい制度やシステム導入当初は間違いやエラーが頻発する時期もあるでしょう。しかし、こと医療をはじめとする社会保障に関しては、それは許されるものではありません。可能な限り完璧に近い状態で進めなければならないのが社会保障です。何故ならそこに国民の生命や財産に直接関わる大切な情報があるからです。それでも誤りや間違いは生じるのです。だからこそ漸次移行するというスタンスでなければならないはずです。過ちが頻発する時期に居合わせた人々は大きな損害を被り、多大な損失や被害を受けることになります。最悪なことに現行のシステムではそれを保証することも賠償することもありません。ただ壊れたレコードのように「大丈夫」と繰り返すだけなのが政府(国)の姿勢です。
我が国の医療制度は、日本国憲法第11条(「基本的人権の尊重:すべての国民が有する健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」)に基づくものです。これは国家が保障しなければなりません。今行われている医療DXは本当に国民の最低限度の生活を保障するものでしょうか? 我が国の医療は国民皆保険制度の上に成り立っています。昨年の診療報酬改定で長期収載医薬品の選定療養費化が強行されました。これは今まで保険診療で守られていた処方薬が、「中身が一緒であれば値段の安いほうだけ保険診療にしますから、高いほうを選ぶならばその差額は自分で払いなさい」、つまり「自費で買いなさい」ということです。チョコレートを買う時、同じミルクチョコレートでも「私はA社のほうが味が好きだからA社にしたい」って言っても、「お父さんはB社のチョコレートを薦めているんだからA社だったら自分で買いなさい」って言ってるようなものです。お金を払うのはお父さんです。これと同じことが、投薬の現場で起きています。保険診療は患者さんに合った診療をすることなのです。薬を変える理由は人それぞれであってしかるべきであり、選定療養費化は問題です。
昨年11月28日東京地裁で非常に重要な訴訟の判決が出ました。懸案のオンライン資格確認訴訟です。マイナ保険証によるオンライン資格確認の実質義務化は、療養担当規則で医療機関に義務化することにほかならず、憲法で定める基本的人権尊重の健康保険法の委任の範囲を逸脱していると訴えたのですが、驚くことに地裁は国の主張のみを取り上げて却下という結論を出しました。「御上の言うことに盾突くことはならん」ということなのでしょう。アナクロニズムも甚だしい。「江戸時代か?」と突っ込みたくなるような判決ですが、安倍政権から連綿と続く腐敗した1強政権の弊害がいまだに続いています。
今年は医師の働き方改革や医師の偏在、地域の病床数の調整、削減など「新たな地域医療構想」に向けての議論が加速されます。地域医療構想がどのような展望を示すかしっかり見極め確認し、理解して対策を立てなければならない年です。
保険医協会も少しずつですが疲弊した医療の現場を立て直すよう、会員の皆さんに意見を示してまいります。皆さんもどんどんご意見ご批判、疑問など投げかけて下さい。皆さんの気持ちに一生懸命応えて参りますのでこの1年間叱咤激励よろしくお願い致します。
会長 阿部政則 (会報1月号「年頭所感」)