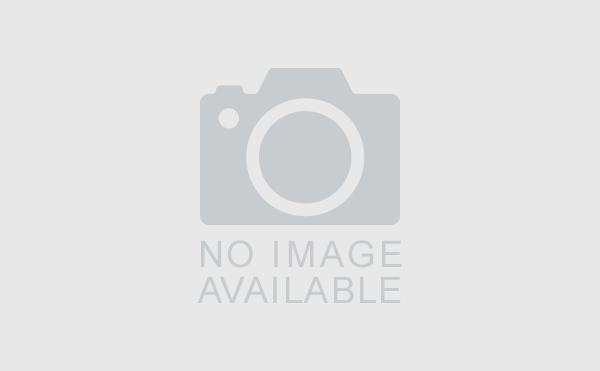国は国民から信頼されているのか?(会報4月号「主張」)
国連は2025年も「国際幸福デー」の3月20日に、恒例の国別幸福度ランキング(世界幸福度報告)を公表しました。気になる日本の順位は、対象となる147の国や地域の中で昨年の51位から55位に順位を下げ、G7の中で最下位のままでした。この「世界幸福度報告」は、国連の関連組織などが中心となって作られたもので、フィンランドが8年連続で1位となったほか、デンマーク、アイスランドが続くなど、福祉や教育が充実している北欧諸国が上位を占めます。調査項目は、国民一人当たりの所得(GDP)、男女平均健康寿命、社会的保障支援、社会的平等、自由度や寛容度、国(政府)への信頼度の6項目を指標としています。健康寿命は1位、社会保障支援は17位、国民一人当たり所得は35位(参考までに隣国の韓国は33位)となっています。健康寿命以外は低下傾向ではありますが、総合判定の55位を上回っているのに、他の社会的平等、個人の自由度や世間の寛容度とともに順位を押し下げているのが「国への信頼度」でした。
高負担高福祉国家である北欧の国々の国民負担率は日本より高い数字(フィンランド61%、日本48%)ですが、幸福度は高くなっています。つまり、納付するお金(税金・社会保障負担など)を国が正しく透明性と責任をもって配分、使用していることに国民が信頼を置いているから、「高負担」でも幸福度が高いのでしょう。政治にまつわるお金の不透明さ、一部官僚の天下り先の退職金額などの報道を見聞きすると、国民感覚から外れている為政者を「信頼する」気持ちが低下するのは当然のことでしょう。政治に関わるお金も我々同様厳格に報告(一部は禁止)し、官僚の退職後も庶民が納得する処遇にするなど、国は信頼向上に努めるべきと思います。
「65歳以上の国民不安の3K」をご存じでしょうか。ローマ字の頭文字で「(お)金KANE・健康・孤独」とされています。最近はこれに「介護」や「米・食い物」など不安の「K」項目が増えて5Kとも言われます。とはいえ、60歳以上の年齢層が有する金融資産は1200兆円とも言われ、金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」によると、60代の平均金融資産の保有額は2317万円となり漸増しています。中央値は750万円なので、平均とは大きく離れた数字になっていますが、少なくとも老後に備えて国民は貯金を殖やしている現状があります。景気が悪くて収入も増えていないのに、生活が苦しくても、個人は貯蓄を積み足しているのです。これは「長生きするかもしれない」老後や将来への不安から、ある程度の金融資産があっても老後が心配で使えない、あるいは使う心境になれないという悲しい現実です。「貯めても不安、使うのも不安」なのでしょう。大前研一氏は、「国民が将来や老後に不安があるのでお金を使えない心理(老後不安不況)」を、すでに2007年から指摘しています(『心理経済学』:講談社 2007)。政府が将来や老後の不安を解消するような政策を実行すれば市場にお金が流れてくる、という説明です。
日本は中負担中福祉と言われていますが、本当に正確な試算が示され、国や行政が信頼されることをしてくれれば、もう少し私達も安心してお金(貯蓄)を消費に回せる気がします。国債発行残高や社会保障費不足ばかりを声高に報道し、国民の不安を煽っています。日本国民の幸福感を上げるには、まず国(政府や官僚による政策)に対する国民からの信頼度を上げることが不可欠と思います。そうすれば国民の老後や将来の不安感が減少し、自分のお金を使って幸福な時間を過ごすことができるようになるのではないでしょうか。(山口県保険医協会報2025年4月号「主張」)